日々の活動日記 STAFF BLOG
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 3月 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
NEW最近の投稿
CATEGORYカテゴリー
- DIY
- アパート・マンション
- ベランダ・陸屋根防水
- 上田市
- 中野市
- 住宅リフォーム
- 佐久市
- 信濃町
- 千曲市
- 古民家・空き家リフォーム
- 塀・門扉の再生
- 塗床工事
- 塗料のグレード・種類
- 外壁屋根の塗装工事
- 外壁屋根の現場調査・現地調査
- 外壁屋根の色・カラーシミュレーション
- 外構エクステリア
- 家具再生・リメイク
- 山ノ内町
- 工場・大規模建物
- 店舗改修・店舗リフォーム
- 断熱・遮熱塗料
- 木部の劣化診断・塗装
- 火災保険申請工事
- 窓・玄関のリフォーム
- 立会検査・引き渡し
- 虫の対策・被害
- 補助金・助成金・減税制度
- 訪問販売・商談トーク
- 足場設置・足場の知識
- 躯体改修・外壁補修
- 軽井沢町
- 鉄部塗装
- 長和町
- 長野市
- 雨樋調査・工事
- 雨漏り診断・調査
- 雪止め設置・補助金活用
- 須坂市
- 鳥・害獣対策
ARCHIVEアーカイブ
- 2022年3月
- 2021年12月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年2月
- 2013年1月
日々の活動日記
外壁のクモの巣対策を徹底解説!掃除方法から予防策までまるわかりガイド
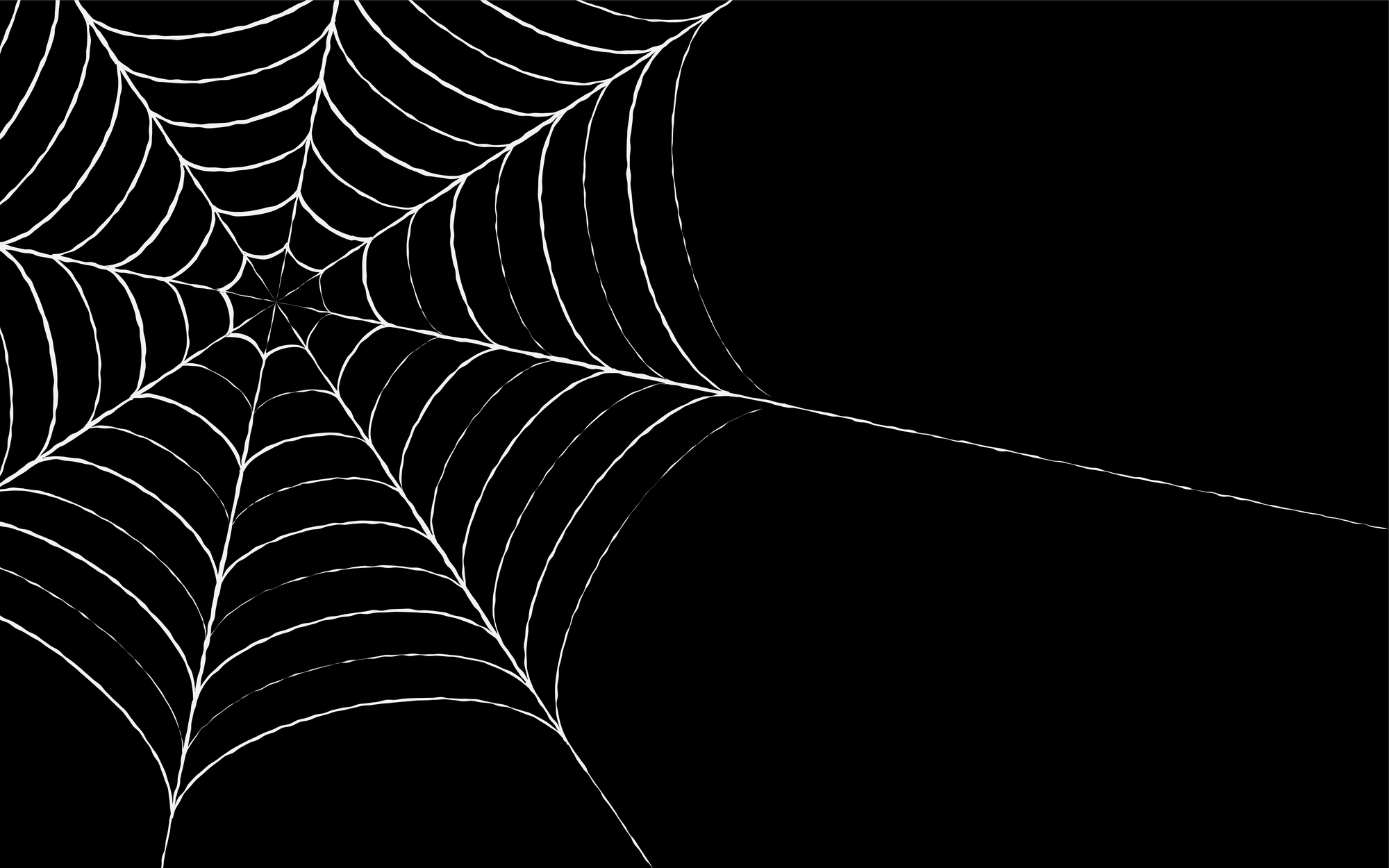
外壁にクモの巣がたくさん張り付いているのを見て、「なんとかしたいけれど、どう掃除すればいいか分からない」「一度取り除いても、またすぐ巣が張られてしまって困る…」なんて経験ありませんか?
特に軒下や玄関まわりにクモの巣があると、どうしても見た目が悪くなりますし、来客時にも気を遣ってしまうものです。
さらに、室内への侵入が気になる場合もあり、ストレスを感じている方は多いでしょう。
そこで本記事では、外壁のクモの巣をすっきり掃除する方法から、クモが巣を張りにくくする具体的な対策、そしてクモの侵入を防ぐポイントまで徹底的に解説します。
洗剤を使ったお手軽なお掃除テクニックや、忌避剤・スプレーによる予防策など、多角的なアプローチでクモの悩みを解決できるようまとめました。
ぜひ、毎日の暮らしをより快適にするためのヒントとしてお役立てください。
目次
外壁のクモの巣、なぜこんなに増える?知っておきたい原因と影響
外壁にクモの巣が多く見られるのは、「クモが住み着く環境」になりやすい要因がいくつか重なっているためです。
クモは害虫を捕まえるために巣を張る習性があり、特に夜になると玄関の明かりに集まる小さな虫を狙って出没します。
また、軒下や窓のサッシまわりなど、雨風がしのぎやすい場所はクモにとって格好の住処になりがちです。
クモ自体は、他の害虫(ゴキブリや蚊など)を捕食する存在として一定の役割を果たすとも言われますが、一方で、見た目の不快感や掃除の手間といったデメリットも無視できません。
さらに、クモの糸にはほこりや汚れが付きやすく、外壁がなんとなくくすんで見えてしまう原因にもなります。美観を保つためにも、早めの対策が必要です。
外壁のクモの巣を取り除く!基本の掃除方法と手順
クモの巣を取り除くには、ほうきや雑巾、専用ブラシなどを使った物理的な方法がもっとも手軽で効果的です。
ここでは、具体的な掃除の手順や注意点を詳しく解説します。高所や狭い箇所にも対応できるよう、それぞれの道具の使い方を押さえておきましょう。
クモの巣を取り除く際に準備するもの
手袋
クモの巣を掃除する際、まず最初に準備すべきなのが手袋の着用です。
クモそのものに咬まれるリスクを避けるだけでなく、巣に付着した汚れやほこりから手肌を守る目的もあります。
クモの巣には細かなチリや虫の死骸などが絡んでいることが多く、直接素手で触れるのは衛生上も好ましくありません
。滑りにくい素材の手袋を選び、作業中のグリップ力も確保することで、より安全に、快適に掃除を進めることができます。
ほうき(柄の長いタイプ)
高所に張られたクモの巣には、柄の長いほうきを使用するのが効果的です。
特に先端に水切りネットなど柔らかい素材を被せると、クモの細くべとつく糸もしっかり絡め取ることができ、除去効率が格段に向上します。
直接ほうきで掃くと、糸が飛び散ったりほうきに絡まって取れにくくなることがあるため、ネットでキャッチ力を高める工夫が掃除成功のポイントです。
無理な高所作業を避けるため、脚立や安全な足場を併用することも大切です。
濡れ雑巾
ほうきで取りきれなかった巣の残骸や、壁に付着した細かい糸は、水で軽く湿らせた雑巾を使って拭き取ります。
乾いた雑巾よりも、適度に濡れた状態の方がクモの糸が雑巾に絡みやすく、残さず除去できるため効果的です。
掃除後の仕上げ拭きとしても活用でき、外壁の見た目をきれいに整えることができます。
特に目立つ場所では、雑巾拭きまで丁寧に行うことで、仕上がりに大きな違いが出ます。
クモの巣取りブラシ
市販されているクモの巣取りブラシは、専用設計ならではの使いやすさがあります。
ブラシ部分に粘着性のあるシートを巻き付けるタイプが多く、べとべとした巣や巣に絡んだ小さな虫も一度でしっかりキャッチできるのが特徴です。
狭い隙間や複雑な形状の外壁部分、窓枠まわりなど、ほうきや雑巾では届きにくい場所にもスムーズに対応でき、作業時間を短縮できます。
効率重視の場合は、専用ブラシを取り入れるのがおすすめです。
洗剤(汚れがひどい場合)
クモの巣が張られていた部分に汚れや泥がこびり付いている場合は、中性洗剤を薄めた水溶液で拭き掃除を行います。
ただし、外壁材によっては洗剤との相性があるため、事前に素材適合性を確認することが必要です。
高圧洗浄機を使用せず、やさしく拭き取る方法が基本です。
汚れをきれいに除去することで、クモの再発生リスクも抑えられ、外壁の見た目も清潔に保つことができます。
素材を傷めない配慮と、適切な洗剤選びが成功のカギです。
掃除の手順
手袋を装着し、安全を確保
クモの巣掃除を行う際、まず必ず手袋を装着して安全対策を講じましょう。
素手で巣に触れると、隠れていたクモに咬まれるリスクがあるほか、巣に付着しているダニやほこりによりアレルギー反応を引き起こす可能性もあります。
特に目に見えない汚染物質が付着していることもあるため、衛生面の観点からも手袋の使用は必須です。
安全かつ衛生的に作業を進めるために、厚手で滑り止め付きの作業用手袋を選ぶとより安心して取り組めます。
ほうき・ブラシで大きな巣を除去
次に、柄の長いほうきやクモの巣取り専用ブラシを使って、大まかな巣の除去を行います。
ほうきの先端に水切りネットをかぶせて使うと、糸がほうきに絡まりやすく、効率よく巣を巻き取ることができます。
専用ブラシを使用する場合は、ブラシ部分にシートを巻き付けて、壁面に軽く押し付けるようにして巣をキャッチするのがポイントです。
無理に力を入れると外壁を傷つける恐れがあるため、優しく確実に除去することを心がけましょう。
濡れ雑巾で拭き取る
大きな巣を取り除いた後は、水で軽く湿らせた雑巾を使って、壁面を丁寧に拭き上げます。
クモの巣は細い糸が残りやすく、目視では取り切れたように見えても、光の加減で後から気づくこともあります。
濡れ雑巾で糸を絡め取るようにゆっくり拭き取ることで、残留物をしっかり除去し、美しい外観を取り戻すことができます。
この工程を丁寧に行うかどうかで、仕上がりの満足度に大きな差が出ます。
汚れがひどい場合は洗剤を使用
外壁に泥汚れやほこりのこびりつきが目立つ場合は、中性洗剤を薄めた水で拭き掃除を行いましょう。
中性洗剤は外壁材への負担が少なく、安全に汚れを浮かせて除去できるため、安心して使用できます。
ただし、洗剤成分が残るとシミや変色の原因になることもあるため、最後には必ず水拭きをして洗剤をしっかり拭き取ることが大切です。
適切な洗浄手順を守ることで、外壁の美観と耐久性を保つことができます。
乾拭きで仕上げ
最後の仕上げとして、柔らかいタオルや乾いた雑巾で外壁をしっかり乾拭きします。
濡れたまま放置すると、水滴跡や洗剤残りによるシミができるリスクがあるため、必ずこの乾拭き工程を入れることが重要です。
特に窓まわりや細かな段差のある部分は水が溜まりやすいため、意識的にタオルで押さえるようにして拭き取ると効果的です。
最後まで丁寧に仕上げることで、清潔感のある美しい外壁を維持できます。
補足: 高所を掃除する際は、脚立やはしごを使用することがありますが、転倒の危険があるため、必ず安定した足場を確保しましょう。
また、ブラシやほうきの柄を伸ばせば、脚立なしでも比較的高い位置まで対応できる場合があります。
クモが再度巣を張りにくくする予防策と対策方法
クモは、一度巣を張った場所を「安全で快適な場所」と認識し、何度も同じ場所に巣を張る習性があります。
そのため、たとえ丁寧に掃除して巣を除去しても、根本的な対策を取らなければ再び巣が作られてしまうことが少なくありません。
特に、軒下や窓枠まわり、外壁の凹凸部分などはクモにとって絶好の巣作りスポットです。
再発防止には、クモが「ここには住みたくない」と感じる環境づくりが欠かせません。物理的な掃除とあわせて、予防策を講じることが、長期的な成果につながります。
忌避剤や殺虫スプレーを活用する
忌避剤(スプレータイプ・テープタイプ)
クモを再度寄せ付けないために最も効果的な方法の一つが、市販のクモ専用忌避剤の活用です。
スプレータイプであれば、外壁、軒下、窓枠、玄関まわりなど、巣が作られやすい場所に広範囲に噴霧できます。
また、テープタイプの忌避剤は、雨や紫外線に強い仕様のものがあり、屋外でも長期間効果を維持できる点が魅力です。
製品を選ぶ際は、「雨に強いタイプ」「長持ちタイプ」を基準に選ぶと、少ない手間で継続的な効果が期待できます。
物理的なバリアを作るイメージで、施工範囲をしっかりカバーしましょう。
ミントやハッカ油などのアロマ成分
市販の化学薬剤を使わず、もっと自然な方法を好む方には、ミントやハッカ油などのアロマ成分を活用した対策がおすすめです。
クモは、ミント、レモングラス、シダーウッドなどの香りを嫌うと言われています。
スプレーボトルに水で希釈したアロマオイルを入れ、外壁や窓周りに定期的に噴霧することで、一時的にクモの寄り付きリスクを低減する効果が期待できます。
ただし、アロマスプレーは雨や時間経過で効果が薄れるため、こまめな再噴霧が必要です。天然素材を活かしたクモ対策として、手軽に取り組める方法の一つです。
隙間テープで侵入経路を封鎖
クモは、わずか数ミリの隙間からでも室内や軒下に侵入してきます。
特に、窓やドアサッシ、エアコン配管周辺など、建物の構造上できやすい微小な空洞は、クモにとって絶好の侵入経路です。
この侵入リスクを防ぐためには、気密性の高い隙間テープを使って物理的に経路を封鎖することが有効です。
ドアや窓枠周囲に隙間がある場合は、隙間テープでしっかりと埋め、エアコン配管スリーブの周囲に空洞がある場合は、パテで隙間を充填します。侵入ルートを根本から断つことが、長期的なクモ対策の基本です。
鉢植えや段ボールの処分・整理
クモ自体が餌とするのは、主に小さな虫類です。
ベランダや軒下に置きっぱなしの鉢植えや古い段ボールなどは、虫を呼び寄せる温床になり、結果としてクモを引き寄せてしまいます。
特に、鉢植えの下皿に溜まった水はボウフラ(蚊の幼虫)などを発生させやすく、間接的にクモの餌場を作ってしまうことになります。
不要なものは定期的に処分し、収納可能なものは物置などに整理整頓する。鉢植えの水皿もこまめに水を捨てる。
これらを徹底することで、クモが寄り付きにくい、清潔な環境づくりが実現します。
アース製薬などのクモスプレーを利用する
市販されているクモ専用スプレー(例:アース製薬の製品など)は、クモが巣を作りやすい軒下や玄関まわりへの定期的な噴霧により、高い忌避効果を発揮します。
特に、撥水性を持つシリコーン配合タイプであれば、雨に強く効果が長持ちしやすいのが特徴です。
スプレー直後に外壁が一時的に濡れたような色に変わることもありますが、ほとんどの場合は乾けば元に戻るため安心して使用できます。
クモの再発防止には、巣を張りたくなる環境そのものを継続的にコントロールすることが重要です。
プロ仕様に匹敵するクモスプレーを上手に活用し、効果的な防除を実践しましょう。
外壁のクモ問題を根本的に減らす!室内への侵入を防ぐ工夫
外壁だけでなく、クモが室内に侵入してしまうと、さらにストレスを感じる方も多いでしょう。
特に、小さなクモは網戸やドアのわずかな隙間からでも入り込む可能性があります。
ここでは、室内への侵入を防ぐための具体的なアイデアを紹介します。
網戸のメンテナンス
クモや小さな虫の室内侵入を防ぐには、まず網戸の状態チェックが基本です。破れや隙間がある網戸は、クモにとって簡単に出入りできる「開かれたドア」と同じです。特に窓やドア周辺は頻繁に開閉するため、網戸がレールから外れていたり、緩んでいたりすると効果が半減します。破れた部分は専用補修シールで応急処置、もしくは速やかに網戸交換を行いましょう。レール部分も汚れがたまると網戸がスムーズに閉まらなくなるため、定期的な清掃で密閉性を維持することが重要です。
照明の工夫
夜間に明るい照明を点けっぱなしにしていると、虫が光に引き寄せられ、その虫を狙ってクモも寄りつきやすくなります。この光による連鎖を防ぐためには、玄関やベランダ周りの照明を虫が集まりにくい**LEDライト(暖色系)**に切り替えるのが効果的です。また、必要のない時間帯には照明を消す、照明器具の設置位置を調整する(高い位置に設置する)など、虫の誘引を最小限に抑える工夫も有効です。外から虫を呼び込まないことが、結果的にクモの室内侵入リスクを大幅に減らします
室内の整理整頓
室内に段ボール、古紙、使わない衣類などを床や隅に放置していると、ダニや小さな虫が繁殖しやすい環境を作り、間接的にクモを呼び寄せる原因になります。これを防ぐには、定期的な整理整頓と掃除を徹底することが不可欠です。特に押し入れ、家具の隙間、窓際など、湿気が溜まりやすい場所は重点的に片付けましょう。クモの餌となる虫を減らし、隠れる場所も与えないことが、クモの定着を防ぐための効果的な室内管理法です。
クモを餌とする害虫対策
クモが室内に侵入する最大の理由は、「そこに餌となる虫がいるから」です。蚊やハエ、チョウバエなどの小型昆虫が室内に多いと、クモも自然と集まってきます。この連鎖を断つためには、室内の害虫対策を総合的に強化することが重要です。虫除けスプレーの使用、換気をこまめに行う、キッチンや排水口周辺を清潔に保つ、食品の管理を徹底するなど、複合的な対策を組み合わせましょう。餌となる害虫を減らすことで、クモの居着く魅力自体を大幅に低減でき、室内環境の清潔さと快適性も同時に向上します。
外壁のクモの巣をしっかり掃除&対策して美観と快適さをキープ
外壁にクモの巣があると、どうしても見た目が不潔な印象になってしまいますし、クモの存在自体も苦手な方にはストレスになるでしょう。
まずはほうきや濡れ雑巾、専用ブラシなどを使った丁寧な掃除で巣を取り除き、そのうえで忌避剤や隙間テープなどを活用した予防策を講じることが重要です。
クモは一度巣を作った場所に再度戻ろうとする習性があるため、掃除と対策をセットで行うことで、巣が張られる確率を大幅に下げられます。
・掃除の基本ステップ
手袋の着用 → ほうきやブラシで巣を除去 → 濡れ雑巾で拭き取る → 汚れがひどいときは洗剤使用 → 乾拭きで仕上げ。
・予防策としての忌避剤・スプレー
クモ専用のスプレーやミントなどの香り成分を利用することで、クモが寄り付きにくい環境を作る。
・隙間テープや鉢植え・段ボールの管理
物理的な侵入を防ぎつつ、虫が増えやすいアイテムを整理することで、クモの発生源を断つ。
・照明や網戸のメンテナンス
虫を呼び寄せない照明への切り替えや、破れた網戸の補修などで室内への侵入リスクを抑える。
こうしたポイントを押さえておけば、クモの巣による外壁の汚れや不快感を大幅に軽減できます。
一度きれいに掃除してからは、定期的にチェックと軽い掃除を行うだけでも、美観と快適さをしっかりとキープできるでしょう。
もしクモの大量発生や害虫の増加が見られる場合は、専門の業者に相談することも視野に入れて、早めに対処してください。
ぜひ本記事を参考に、クモの巣だらけになってしまった外壁をスッキリさせ、安心できる住環境を手に入れてください。

















