しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
NEW最近の投稿
CATEGORYカテゴリー
- ALC造
- DIY
- RC造・コンクリート
- アスファルト舗装
- アスベスト含有
- アパート・マンション
- ウッドデッキ新設・リフォーム
- オーニング・サンシェード・パーゴラ
- オフィスリノベーション
- コーキング・シーリング
- サッシ・窓
- ツートンカラー
- トタン屋根
- ハウスクリーニング
- バリアフリー
- プール・貯水槽
- フェンス・塀
- ペット建材・安全安心
- ベランダ・バルコニー
- モルタル仕上げ
- リフォーム
- 下塗り・塗料
- 中野市
- 二重窓
- 仮設設備・仮設足場
- 住まいのお手入れ
- 佐久市
- 内装クロス・フローリング
- 刷毛・ローラーの種類
- 地域情報・観光スポット
- 基礎防水・塗装
- 塗料の条件・季節との相性
- 塗料の種類・グレード
- 塗料メーカー
- 塗替え時期・サイクル
- 塗装後の見え方
- 塗装後不具合・トラブル
- 塗装方法・塗り方
- 壁の仕上げ材・自然素材
- 外壁サイディング
- 外壁の調査や劣化診断
- 外壁屋根メンテナンス
- 外壁屋根塗装
- 外壁屋根塗装を安くする
- 外壁材・屋根材
- 外構エクステリア
- 天窓・トップライト
- 家具のリメイク塗装
- 小諸市
- 屋根外壁のリフォーム
- 山ノ内町
- 工事の見積もり
- 工事の費用相場と実費用
- 工事中の生活
- 工事期間
- 工場・ビル
- 御代田町
- 悪徳業者・手抜き工事
- 断熱材・遮熱工法
- 新築工事・戸建て住宅
- 施工作業の工程
- 日本家屋・和風住宅
- 暑さ対策・日除けリフォーム
- 木材・木部再生
- 未分類
- 業者の選び方
- 温泉・浴槽
- 火災保険申請・工事
- 物置設置・移動・リフォーム
- 特別教育・資格
- 玄関ドア
- 現場管理と検査
- 窓ガラスフィルム
- 結露・結露対策
- 網戸・ふすま・障子・畳
- 色選び・カラーシミュレーション
- 落ち葉・落葉対策
- 虫対策
- 補助金・助成金
- 訪問販売の手口や事例
- 躯体改修・大規模修繕
- 軽井沢
- 遮熱・断熱塗料
- 鉄部塗装
- 長野市
- 防水トップコート
- 防水工事
- 防犯・防災対策
- 雨戸・シャッター
- 雨樋の劣化・調査・修理
- 雨漏り・目視・散水・赤外線
- 雪止め・雪害対策
- 須坂市の魅力
- 風水
- 飯山市
- 養生
- 駐車場ライン引き
- 高山村
- 鳥・獣対策
ARCHIVEアーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2024年11月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年2月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2010年9月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 1998年4月
コラム
珪藻土の汚れを落とす方法と注意点|カビ・油・ホコリの対処と予防法まで解説!

調湿・脱臭・吸水など、さまざまな機能で人気の高い「珪藻土」。壁材やバスマット、コースターなど、生活のさまざまな場所で使われています。
しかし、多孔質な性質ゆえに“汚れやすい”のも事実。
「バスマットが黒ずんできた…」「珪藻土壁にカビが!」といったトラブルに悩まされたことのある方も多いのではないでしょうか?
この記事では、汚れの種類別の対処法から、傷をつけずにキレイに保つための注意点、汚れにくくするための予防法まで、初心者にもわかりやすく丁寧にご紹介します。
目次
珪藻土とは?汚れやすい理由を知ることで、正しい掃除と予防ができる

珪藻土(けいそうど)は、植物性プランクトン(珪藻)の殻が堆積してできた天然素材。
無数のミクロな穴(多孔質構造)が特徴で、これが調湿・脱臭・吸水といった高い機能を生み出しています。
なぜ珪藻土は汚れやすいのか?
穴が開いている=汚れが染み込みやすい
多孔質構造により、汚れや水分を吸収しやすく、特に油汚れや皮脂、石けんカスなどは内部まで入り込みます。洗剤や水に弱い
洗剤を使ってゴシゴシ洗うと、目詰まりや劣化を起こしてしまいます。削れやすい素材
硬いスポンジやブラシでこすると、表面が傷つきやすいという特徴があります。
高機能ゆえにデリケート。だからこそ「正しい掃除方法」と「日常の予防」がとても大切です。
珪藻土の汚れ別|最適な掃除・補修方法を丁寧に解説!素材を傷めないためのコツも紹介
珪藻土に付く汚れは主に「油汚れ」「カビ」「ホコリ」「皮脂・水アカ」など。
汚れの種類によって落とし方が異なります。
【油汚れ】重曹を使ったパック洗浄が効果的|キッチンや足裏の皮脂に
重曹を水で薄める(ペースト状または水溶液)
キッチンペーパーに含ませて、汚れ部分に貼る
数時間置いたら、乾いた布で拭き取る
皮脂や油分は時間とともに酸化して落ちにくくなるため、気づいたら早めの処理を心がけましょう。ゴシゴシこすらないのがポイントです。
【カビ汚れ】塩素系漂白剤で除菌|壁材・バスマットなどの黒ずみに
塩素系漂白剤(キッチンハイター等)を水で薄める
柔らかい布に含ませて汚れ部分にあてる
換気をしながら数分放置 → 乾いた布で拭き取る
漂白剤を直接吹き付けたり、長時間放置するのはNG。素材が変色したり脆くなったりする原因になります。マスク・手袋も忘れずに。
【ホコリ】柔らかいブラシやホウキで優しく払う
毛の柔らかいハタキやブラシを使う
壁面やコースターなど、表面を傷めないよう軽くなでる
ホコリや花粉などの細かい汚れは、水拭きせず“乾拭き”が基本。毛が硬いブラシは削れの原因になるので避けましょう。
【しつこい汚れ】サンドペーパーで表面を削る|最終手段として有効
300~400番程度の目の細かいサンドペーパーを使用
汚れた部分を“軽く”こすって削る
削った後は、削りカスをしっかり除去
削りすぎは厳禁!ツルツルになると吸湿性が低下するため、最低限の削りでとどめることがポイントです。
珪藻土アイテム別|バスマット・コースター・壁材それぞれの汚れやすいポイントと対策
珪藻土は使い方によって汚れるタイミングや種類が異なります。ここではアイテム別の注意点とメンテナンス方法を解説します。
珪藻土バスマット
汚れやすい箇所:足裏の皮脂、石けんカス、水アカ
対策:使用後はしっかり乾燥させる・定期的に陰干し
吸水力が落ちたと感じたら、サンドペーパーで表面を軽く削ると吸水性が戻ります。
珪藻土コースター
汚れやすい箇所:お茶やコーヒーの色素、油分
対策:使用後すぐ拭き取る・汚れが沈着する前に洗浄
色素は時間が経つと落ちにくくなるので、飲み物の輪ジミは早めに重曹ペーストで対処しましょう。
珪藻土の壁材
汚れやすい箇所:ホコリ、手あか、湿気によるカビ
対策:こまめな乾拭き・換気・除湿を心がける
カビが発生した場合は、部分的に塩素系漂白剤で除菌→乾燥が基本。再発防止には除湿機も効果的です。
珪藻土を汚れにくくするための日常的な予防法|ちょっとした工夫で汚れにくくなる!
汚れた後に掃除するより、「汚れにくくする工夫」をしておくことで、メンテナンスの手間が大きく減ります。
日常でできる珪藻土アイテムの汚れ予防法
使用後は必ず乾燥させる
湿気がこもるとカビ・黒ずみの原因に。陰干しや除湿を意識しましょう。直射日光や水に長時間さらさない
紫外線と水分は劣化を促進させるため、風通しの良い場所で使うのが◎洗剤や石けんの使用は避ける
目詰まりの原因となり、吸水性・消臭性が低下してしまいます。定期的にサンドペーパーでメンテナンス
数ヶ月に1度、軽く表面を削ってリフレッシュすると性能が長持ちします。
珪藻土の掃除でやってはいけないNG行動|傷める原因になるポイントをチェック
誤った掃除方法をしてしまうと、珪藻土の本来の性能が失われてしまうことも。以下のような行動には要注意です。
NG例と理由
ゴシゴシ強くこする
削れやすい素材のため、表面が傷つき吸水性が低下します。アルカリ性・酸性洗剤を使う
目詰まりや素材劣化の原因になります。中性洗剤も基本的にはNG。濡れたまま放置する
湿気がこもってカビの原因に。使用後はしっかり乾燥を。
まとめ|珪藻土は“正しい掃除と予防”がキレイに保つコツ。症状別の対処法で長く使おう!
珪藻土は機能性が高い分、適切なメンテナンスが求められる素材です。
放っておくと汚れがどんどん染み込んでしまうので、日常的なお手入れと汚れの種類ごとの正しい対処法を意識することが大切です。
この記事のポイントまとめ:
珪藻土の汚れには「重曹・漂白剤・サンドペーパー」で対応可能
汚れの種類ごとに落とし方は異なる(油・カビ・ホコリ・皮脂)
洗剤や水の使いすぎ、強くこするのはNG!
バスマットやコースターなど、使用アイテムに応じた予防法も大事
陰干し・除湿・サンドペーパーの活用で吸水性が長持ちする
日々のお手入れで、珪藻土の良さをしっかり活かしていきましょう!
番外編|珪藻土の歴史
珪藻土とは自然が長い年月をかけて生み出した、植物性プランクトンの死骸が海底に堆積してできた土の事をいいます。

珪藻土は全国の様々な地域で採掘することができます。
北海道や秋田・石川・島根・などが有名です。
珪藻土の魅力
珪藻土は内装に使用されることが多いですが、使用する事での効果がなければ意味がありません。
最近増えてきている珪藻土の魅力とは一体何でしょうか?

(1)消臭効果
湿気を吸い取ると同時に臭いの成分も一緒に吸着します。
そのため、ペットやたばこのニオイだけでなくホルムアルデヒドといった有害物質の吸着にも効果があります。
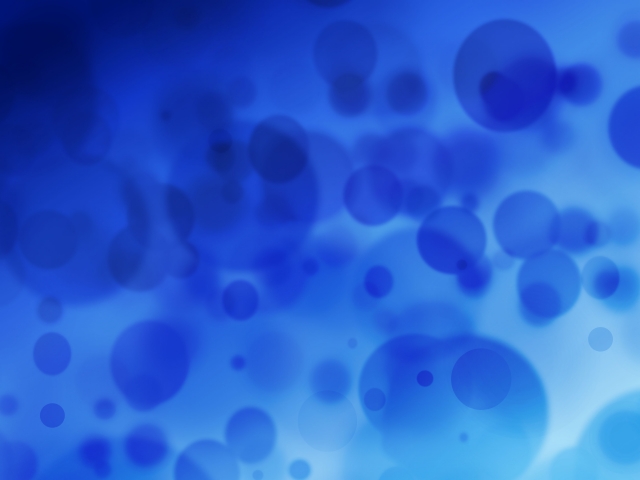
(2)調湿効果
珪藻土は湿度を調節する効果があります。そのため結露も防ぐ効果も期待できます。
湿度を快適な状態に保つので、湿気を好むダニやカビの発生を抑えてくれます。

(3)省エネ効果
珪藻土は無数の気孔が空気の層となっています。
そのため、断熱効果に優れており外気温に影響されにくいといわれています

(4)耐火性に優れている
昔から耐火性に優れていることから、コンロやレンガに使用されていました。
また、珪藻土には化学物質が使用されていないので燃えてしまっても有害物質を排出する事がありません。

健康志向が高まっているからこそ
新築だけでなく、リフォームでも自然素材の使用が多くなってきています。
特にリフォームでは通常の壁紙ではなく珪藻土を塗装する方も増えています。

ただ塗装の場合はコストと時間がかかってしまう難点もあります。
コストや時間を重視される方は、壁紙としても販売されているのでコストパフォーマンスとしては優れているのではないでしょうか?
その他にもバスマットに使用している商品もありますので一度使ってみてください。
内装に珪藻土を使用することで、冬場に多くみられる結露の発生には効果が期待できるのでは。



















