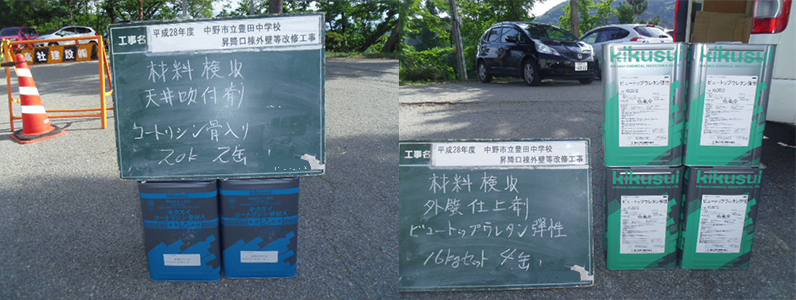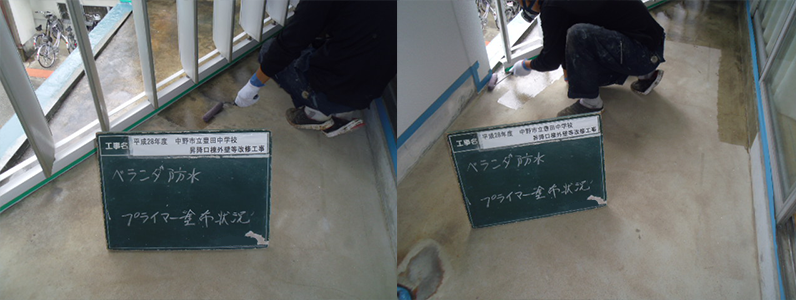しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
NEW最近の投稿
CATEGORYカテゴリー
- ALC造
- DIY
- RC造・コンクリート
- アスファルト舗装
- アスベスト含有
- アパート・マンション
- ウッドデッキ新設・リフォーム
- オーニング・サンシェード・パーゴラ
- オフィスリノベーション
- コーキング・シーリング
- サッシ・窓
- ツートンカラー
- トタン屋根
- ハウスクリーニング
- バリアフリー
- プール・貯水槽
- フェンス・塀
- ペット建材・安全安心
- ベランダ・バルコニー
- モルタル仕上げ
- リフォーム
- 下塗り・塗料
- 中野市
- 二重窓
- 仮設設備・仮設足場
- 住まいのお手入れ
- 佐久市
- 内装クロス・フローリング
- 刷毛・ローラーの種類
- 地域情報・観光スポット
- 基礎防水・塗装
- 塗料の条件・季節との相性
- 塗料の種類・グレード
- 塗料メーカー
- 塗替え時期・サイクル
- 塗装後の見え方
- 塗装後不具合・トラブル
- 塗装方法・塗り方
- 壁の仕上げ材・自然素材
- 外壁サイディング
- 外壁の調査や劣化診断
- 外壁屋根メンテナンス
- 外壁屋根塗装
- 外壁屋根塗装を安くする
- 外壁材・屋根材
- 外構エクステリア
- 天窓・トップライト
- 家具のリメイク塗装
- 小諸市
- 屋根外壁のリフォーム
- 山ノ内町
- 工事の見積もり
- 工事の費用相場と実費用
- 工事中の生活
- 工事期間
- 工場・ビル
- 御代田町
- 悪徳業者・手抜き工事
- 断熱材・遮熱工法
- 新築工事・戸建て住宅
- 施工作業の工程
- 日本家屋・和風住宅
- 暑さ対策・日除けリフォーム
- 木材・木部再生
- 未分類
- 業者の選び方
- 温泉・浴槽
- 火災保険申請・工事
- 物置設置・移動・リフォーム
- 特別教育・資格
- 玄関ドア
- 現場管理と検査
- 窓ガラスフィルム
- 結露・結露対策
- 網戸・ふすま・障子・畳
- 色選び・カラーシミュレーション
- 落ち葉・落葉対策
- 虫対策
- 補助金・助成金
- 訪問販売の手口や事例
- 躯体改修・大規模修繕
- 軽井沢
- 遮熱・断熱塗料
- 鉄部塗装
- 長野市
- 防水トップコート
- 防水工事
- 防犯・防災対策
- 雨戸・シャッター
- 雨樋の劣化・調査・修理
- 雨漏り・目視・散水・赤外線
- 雪止め・雪害対策
- 須坂市の魅力
- 風水
- 飯山市
- 養生
- 駐車場ライン引き
- 高山村
- 鳥・獣対策
ARCHIVEアーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2024年11月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年2月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2010年9月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 1998年4月
コラム
【躯体の劣化を防ぐモルタル補修のすべて】ひび割れ・浮きの補修手順と長持ちさせるコツ

住宅やビルの躯体に使われるモルタルは、時間の経過とともに劣化が進む素材です。
モルタルのひび割れや浮きを放置していると、雨水の侵入や鉄筋の腐食といった深刻なダメージにつながる可能性があります。
この記事では、モルタルの劣化症状ごとの補修方法(注入・塗布・成形)や補修の重要性、長持ちさせるポイントまで、専門知識がなくても理解できるように詳しく解説します。
目次
躯体とは?モルタルとコンクリートの違い
躯体(くたい)とは
建物の構造を支える柱・梁・壁・床などの構造体そのものを指します。鉄筋コンクリート造(RC造)では、モルタルやコンクリートが主な構成材料です。
モルタルとコンクリートの違い
| 項目 | モルタル | コンクリート |
| 成分 | セメント+砂+水 | セメント+砂+砂利+水 |
| 主な用途 | 外壁・下地仕上げ・補修 | 構造体(柱・床など) |
| 特徴 | 仕上がりが滑らか、硬化が早い | 耐久性が高く重量がある |
モルタルは外壁の仕上げ材や下地として用いられますが、劣化すると表面から雨水が浸透し、内部の鉄筋まで影響を及ぼす恐れがあります。
なぜモルタルは劣化するのか?主な原因とは
経年劣化
●紫外線や雨風にさらされることでセメントの結合力が低下
●表面が乾燥と収縮を繰り返し、ひび割れが生じる
温度変化・凍結
●冬季に水分が凍ると体積が増え、モルタルが内部から破壊される
地震や振動
●躯体が揺れることで、表面にストレスがかかり微細なクラックが発生
不適切な施工
●練り混ぜ不足や下地との密着不良により、浮きや剥離が起こりやすくなる
躯体に現れる劣化症状【ひび割れ・浮き】
ひび割れ(クラック)
●モルタルの乾燥・収縮・振動で起こる
●幅0.3mm以上で構造クラックと見なされ、早急な補修が必要
浮き(はがれ)
●モルタルと下地(コンクリートや金網)の接着力が低下し、空洞ができる
●外からは分かりにくいが、軽く叩くと空洞音がする
モルタルのひび割れ補修方法と手順
適用ケース
●幅0.3mm程度の軽微なクラック
●表面上のひび割れに限られる
補修手順
●クラック部分の清掃
→ 汚れ・カビ・旧塗膜を除去
●専用補修材を塗布
→ ポリマーセメントやエポキシ系補修材を使用
●ヘラで均一にならす
→ 下地と段差がないように仕上げる
●表面を乾燥させ、再塗装する
モルタルの浮き補修方法と工程
浮き補修では、注入工法+ピンニング補強が主流です。
補修手順
●注入位置のマーキング
→ タイルの目地や目視で範囲を特定
●穴あけ(穿孔)
→ コンクリート用ドリルで注入穴を開ける(直径6~8mm)
●孔内の清掃
→ 粉塵や水分を完全に除去
●エポキシ樹脂を注入
→ 高強度接着剤で浮いたモルタルを下地に固定
●アンカーピン挿入
→ 強度を補強するためのステンレスピンを差し込む
●モルタルで成形・仕上げ
→ 穴埋め+表面をならして完了
微細なひび割れには「被覆工法」
被覆工法とは?
幅0.2mm以下の微細なひび割れに対して、塗布材でひび割れ上から覆い、劣化を防ぐ方法です。
使用材料
●弾性防水塗料(可とう性あり)
●ポリマーセメントモルタル
特徴
●雨水や紫外線の浸入を防ぐ
●補修跡が目立たない
●仕上げ塗装と同時に施工可能
モルタル補修後の塗装とメンテナンスが重要な理由
モルタル補修が終わったら、表面を塗装で保護することが必須です。
なぜ塗装が必要?
●紫外線や雨風を遮断し、再劣化を防止
●防水性・防カビ性を付与
●美観を整え、補修跡を隠す
使用する塗料の例
●弾性塗料(クラック追従性あり)
●水性アクリル・シリコン・フッ素塗料など
補修を後回しにするとどうなる?放置のリスク
劣化の進行が早まる
●ひび割れから水が侵入し、鉄筋が錆びて膨張 → モルタルが破裂・剥落
雨漏り・漏水の発生
●特にバルコニーや外壁面の劣化は室内まで水が浸透するリスクあり
資産価値の低下・修繕費の増加
●放置すると補修費が10倍以上になることも
信頼できる業者選びのポイント
施工実績が豊富か?
→ モルタル補修・外壁補修の実績写真を公開している業者が信頼性あり
調査・診断が丁寧か?
→ 打診調査・赤外線調査などを用いて、劣化の範囲を数値で把握する業者を選ぶ
見積もりに材料名・工程が明記されているか?
→ 「エポキシ注入」や「下塗り+上塗り」など、工程が具体的に記されていれば安心
まとめ:早期補修と保護塗装で長寿命な建物へ
モルタルの劣化は、外からは小さなひびに見えても、内部では重大なダメージが進行していることがあります。
躯体の健全性を保つには、早期発見・早期補修・表面保護(塗装)の3ステップが不可欠です。
この記事のまとめ
● モルタルの劣化はひび割れ・浮きとして現れる
● ひび割れ補修は清掃→補修材塗布→塗装
● 浮き補修は穴あけ→樹脂注入→アンカーピン→埋め戻し
● 幅0.2mm以下の微細なひび割れには被覆工法が効果的
● 補修後は必ず塗装で保護し、再劣化を防止
●放置すると構造の劣化・雨漏り・高額修繕に発展する
躯体の劣化は見逃されがちですが、建物全体の安全性や寿命に大きく関わる重要なポイントです。
「もしかして…」と思ったら、早めの点検・補修を検討しましょう。