しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
NEW最近の投稿
CATEGORYカテゴリー
- ALC造
- DIY
- RC造・コンクリート
- アスファルト舗装
- アスベスト含有
- アパート・マンション
- ウッドデッキ新設・リフォーム
- オーニング・サンシェード・パーゴラ
- オフィスリノベーション
- コーキング・シーリング
- サッシ・窓
- ツートンカラー
- トタン屋根
- ハウスクリーニング
- バリアフリー
- プール・貯水槽
- フェンス・塀
- ペット建材・安全安心
- ベランダ・バルコニー
- モルタル仕上げ
- リフォーム
- 下塗り・塗料
- 中野市
- 二重窓
- 仮設設備・仮設足場
- 住まいのお手入れ
- 佐久市
- 内装クロス・フローリング
- 刷毛・ローラーの種類
- 地域情報・観光スポット
- 基礎防水・塗装
- 塗料の条件・季節との相性
- 塗料の種類・グレード
- 塗料メーカー
- 塗替え時期・サイクル
- 塗装後の見え方
- 塗装後不具合・トラブル
- 塗装方法・塗り方
- 壁の仕上げ材・自然素材
- 外壁サイディング
- 外壁の調査や劣化診断
- 外壁屋根メンテナンス
- 外壁屋根塗装
- 外壁屋根塗装を安くする
- 外壁材・屋根材
- 外構エクステリア
- 天窓・トップライト
- 家具のリメイク塗装
- 小諸市
- 屋根外壁のリフォーム
- 山ノ内町
- 工事の見積もり
- 工事の費用相場と実費用
- 工事中の生活
- 工事期間
- 工場・ビル
- 御代田町
- 悪徳業者・手抜き工事
- 断熱材・遮熱工法
- 新築工事・戸建て住宅
- 施工作業の工程
- 日本家屋・和風住宅
- 暑さ対策・日除けリフォーム
- 木材・木部再生
- 未分類
- 業者の選び方
- 温泉・浴槽
- 火災保険申請・工事
- 物置設置・移動・リフォーム
- 特別教育・資格
- 玄関ドア
- 現場管理と検査
- 窓ガラスフィルム
- 結露・結露対策
- 網戸・ふすま・障子・畳
- 色選び・カラーシミュレーション
- 落ち葉・落葉対策
- 虫対策
- 補助金・助成金
- 訪問販売の手口や事例
- 躯体改修・大規模修繕
- 軽井沢
- 遮熱・断熱塗料
- 鉄部塗装
- 長野市
- 防水トップコート
- 防水工事
- 防犯・防災対策
- 雨戸・シャッター
- 雨樋の劣化・調査・修理
- 雨漏り・目視・散水・赤外線
- 雪止め・雪害対策
- 須坂市の魅力
- 風水
- 飯山市
- 養生
- 駐車場ライン引き
- 高山村
- 鳥・獣対策
ARCHIVEアーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2024年11月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年2月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2010年9月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 1998年4月
コラム
珪藻土vs漆喰|見た目・機能・メンテナンスの違いと正しい選び方とは?自然素材の壁材で後悔しないために

「珪藻土と漆喰って何が違うんだろう?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
「どちらを選べばいいのか分からなくて困っている…」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、珪藻土と漆喰の違いに興味を持つ方に向けて、
◆珪藻土の特徴
◆漆喰の特徴
◆選び方のポイントと注意点
をご紹介していきます。
壁材選びに迷っている方にとって、この記事を読むことで自分に合った素材を見つける手助けとなるでしょう。ぜひ参考にして、理想の住まい作りに役立ててください。
珪藻土と漆喰の違いを徹底比較!
珪藻土と漆喰はどちらも自然素材を用いた壁材として人気があります。
珪藻土は、微細な穴が多いため湿気を吸収しやすく、室内の湿度を調整する機能があります。
一方、漆喰は、硬化すると非常に強固になり、長期間にわたってその効果を発揮します。
また、耐久性や耐火性が求められる場所に適しています。
珪藻土の主成分

珪藻土の主成分は「珪藻の化石」であり、これは「藻類の一種」である珪藻が長い年月をかけて堆積したものです。
珪藻土はその多孔質な構造が特徴で、吸湿性や調湿性に優れています。
室内の湿度を効果的に調整し、結露の発生を抑えることが可能です。特に日本のような湿度が高い環境では、珪藻土の壁材が快適な住環境をつくりだします。
漆喰と比較すると、珪藻土は自然な風合いを持ち、インテリアとしても人気があります。
また、珪藻土は消臭効果も期待でき、室内の空気を清浄に保ちます。
一方で、珪藻土は水濡れに弱く、汚れがつきやすいというデメリットもあります。
したがって、使用する場所や目的に応じた利用方法が望ましいです。
漆喰の主成分

漆喰消の主成は石灰(水酸化カルシウム)であり、古くから日本の建築に利用されてきた伝統的な壁材です。
高い耐久性を持ち、適切な施工を行えば数十年にわたり美しい状態を保つことができます。
漆喰は「抗菌性」と「防カビ性」に優れており、室内の空気を清潔に保つ効果があります。「耐火性」にも優れており、火事の際に安全性を高める役割を果たします。
漆喰のもう一つの特徴として、湿度を調整する能力があり、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を実現します。
自然素材であるため、環境にも優しく、健康を意識した住まいに適しています。
吸湿・調湿性能は珪藻土が優れている?

吸湿・調湿性能において、珪藻土は非常に優れています。
前述したとおり、多孔質構造を持ち、空気中の湿気を吸収・放出する機能があります。
室内の湿度を適切に保ち、結露の発生を抑えることができます。
一方、漆喰の主成分である「消石灰(水酸化カルシウム)」も一定の調湿効果を持つものの、珪藻土ほどの吸湿性はありません。
消臭効果は珪藻土と漆喰どちらが良い?
消臭効果に関しては、珪藻土と漆喰のどちらも優れた性能を持っています。
珪藻土は「多孔質構造」により、空気中の臭いを吸着する能力が高いです。
一方、漆喰は「アルカリ性」の特性を活かして、臭いの元となる菌を抑えることができます。
即効性を求める場合は珪藻土が適していますが、長期的な消臭効果を期待するなら漆喰が有効です。また、漆喰は抗菌効果もあるため、臭いだけでなく空間の清潔さを保つのにも役立ちます。
抗菌・防カビ性能が高いのは漆喰
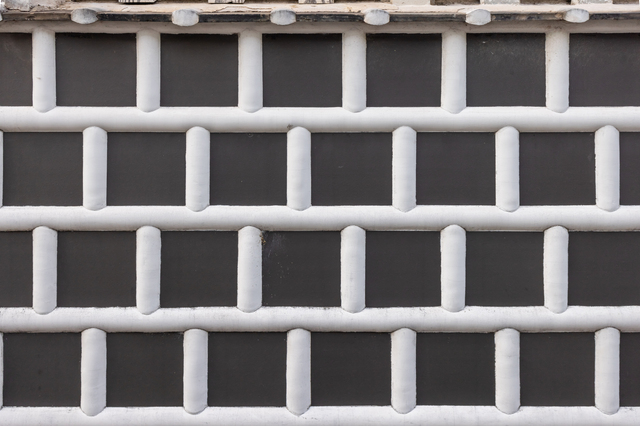 抗菌・防カビ性能に優れる漆喰は、古くから日本の建築に利用されてきました。
抗菌・防カビ性能に優れる漆喰は、古くから日本の建築に利用されてきました。
漆喰の主成分である「消石灰(水酸化カルシウム)」には、カビや細菌を抑制する効果があるため室内環境を清潔に保つことが可能です。
特に湿気の多い日本の気候において、漆喰はその性能を発揮します。
また、漆喰は化学薬品を含まない自然素材であるため、健康への影響も少なく、アレルギー体質の方にも安心して使用できます。
耐久性が高く長持ちするのはどちら?
耐久性の面で比較すると、「漆喰」は非常に優れています。
漆喰は硬化後に強固な層を形成し、長期間にわたってその状態を維持します。
日本の伝統的な建築物にも用いられていることから、その耐久性は歴史的に証明されています。
一方、「珪藻土」は柔らかく、衝撃や摩擦に対してやや弱い傾向があります。
しかし、珪藻土も適切なメンテナンスを行うことで、ある程度の耐久性を保つことが可能です。
耐火性に優れているのは漆喰?珪藻土?

耐火性の面で「漆喰」と「珪藻土」を比較すると、漆喰は非常に優れた特性を持っています。不燃材料として建築基準法で認められており、耐火性に優れています。
実際、漆喰は古くから城や寺院などの防火対策として使用されてきました。
一方、珪藻土も耐火性を持っていますが、漆喰ほどの強力な耐火性能は期待できません。
火災対策を重視する場合は、漆喰を選ぶことが推奨されます。
仕上がりの質感・見た目の違いを比較
珪藻土は「珪藻の化石」を主成分とし、微細な穴が無数に存在するため、マットで柔らかな質感が特徴です。
光を柔らかく反射し、落ち着いた雰囲気を演出します。
一方、漆喰の壁は、光を反射して明るい印象を与えるため、空間を広く見せる効果があります。
また、漆喰の白色は空間を清潔感のあるものにするため、モダンなインテリアにも適しています。
珪藻土は自然な風合いを重視する方に、漆喰はシャープで洗練された印象を求める方におすすめです。
施工費用・価格は珪藻土と漆喰どちらが安い?
施工費用を比較すると、一般的に「漆喰」の方が「珪藻土」よりも安価に施工できます。これは、漆喰が「消石灰」を主成分とし、材料費が比較的低く抑えられるためです。
一方、珪藻土は「珪藻の化石」を主成分としており、特に高品質な製品は価格が高くなる傾向があります。
また、施工には専門的な技術が必要で、職人の技術料が価格に影響します。DIYでの施工も可能ですが、仕上がりの質を求めるならプロに依頼しましょう。
施工面積やデザインの複雑さによっても費用は変動します。
どちらを選ぶかは、予算や求める機能性によって決めると良いでしょう。
珪藻土と漆喰、壁材としてどちらを選ぶべき?
珪藻土と漆喰を壁材として使う際には、用途や設置場所によって最適なものを選びましょう。
例えば、湿気の多い洗面所や脱衣所には、吸湿性に優れた珪藻土が適しています。
一方、リビングや玄関のように人が集まる場所では、抗菌性や耐久性の高い漆喰が最適です。
小さな子どもがいる家庭では、抗菌性に優れた漆喰が安心ですし、インテリア性を重視する場合は、自然な風合いを持つ珪藻土が魅力的です。
珪藻土・漆喰をDIY施工する前に知っておくべきポイント

珪藻土や漆喰をDIYで施工するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
DIYでの施工は、手軽に取り組める反面、失敗すると修正が難しいため、事前の準備が大切です。例えば、初心者でも扱いやすい珪藻土や漆喰製品を選ぶことで、施工のハードルを下げることができます。
また、施工後のメンテナンス方法を理解しておくことで、長期間美しい状態を保つことが可能です。
具体的には、初心者向けの製品としては、既に調合されたパックの珪藻土や漆喰があります。これらは水を加えるだけで使用できるため、手軽に施工が可能です。
施工後のメンテナンスとしては、定期的な掃除や、汚れがついた場合の対処法を知っておくと安心です。以下で詳しく解説していきます。
施工後のメンテナンス方法や掃除のコツ
珪藻土や漆喰の壁は、施工後のメンテナンスが重要です。
まず、珪藻土は「吸湿性」が高く、湿気を吸収しやすいため、定期的に乾燥させることが大切です。
特に梅雨時期や湿度の高い季節には、換気を心がけましょう。
一方、漆喰は「耐久性」が高く、汚れが付きにくいですが、表面に付いた汚れは早めに落とすことが必要です。
柔らかい布で乾拭きし、水拭きは避けるのがベストです。
両素材とも、強い洗剤や研磨剤の使用は避け、優しく扱うことが長持ちのコツです。
定期的なメンテナンスを行うことで、珪藻土と漆喰の美しさを長く保つことができます。
漆喰と珪藻土の壁はどのくらいの期間持つ?

漆喰と珪藻土の壁は、どちらも耐久性に優れていますが、その持ちの良さには違いがあります。
漆喰は「耐火性」と「防水性」に優れています。適切にメンテナンスを行うことで50年以上持つと言われます。
一方、珪藻土は「吸湿性」が高く、湿気を吸収することで室内環境を快適に保ちますが、水濡れや汚れに弱いため、定期的なメンテナンスが必要です。珪藻土の寿命は20年から30年程度とされています。
ただ、どちらも、施工の質や使用環境により耐久性は変わります。
最後に
今回は、珪藻土と漆喰の違いに興味を持つ方に向けて、
・珪藻土と漆喰の基本的な特性
・選び方のコツと注意点
について、お伝えしてきました。
どちらの素材があなたのライフスタイルに合っているのか、じっくりと考えてみてください。
外壁屋根塗装のお見積りはしろくまペイントへ
外壁や屋根の無料診断やお見積りは、しろくまペイントにお気軽にご相談ください
長野市はじめ、信州新町、中条、小川、白馬村、小谷村、麻績村、坂城町、千曲市、須坂市、飯綱町、信濃町、中野市、山ノ内町、木島平村、飯山市、野沢温泉村の雨どい外壁屋根塗装工事もお任せください



















