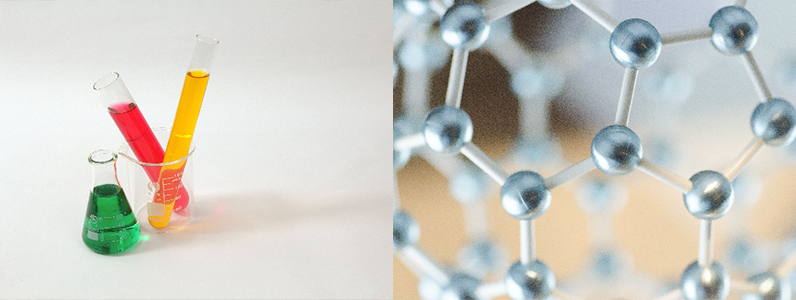しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
NEW最近の投稿
CATEGORYカテゴリー
- ALC造
- DIY
- RC造・コンクリート
- アスファルト舗装
- アスベスト含有
- アパート・マンション
- ウッドデッキ新設・リフォーム
- オーニング・サンシェード・パーゴラ
- オフィスリノベーション
- コーキング・シーリング
- サッシ・窓
- ツートンカラー
- トタン屋根
- ハウスクリーニング
- バリアフリー
- プール・貯水槽
- フェンス・塀
- ペット建材・安全安心
- ベランダ・バルコニー
- モルタル仕上げ
- リフォーム
- 下塗り・塗料
- 中野市
- 二重窓
- 仮設設備・仮設足場
- 住まいのお手入れ
- 佐久市
- 内装クロス・フローリング
- 刷毛・ローラーの種類
- 地域情報・観光スポット
- 基礎防水・塗装
- 塗料の条件・季節との相性
- 塗料の種類・グレード
- 塗料メーカー
- 塗替え時期・サイクル
- 塗装後の見え方
- 塗装後不具合・トラブル
- 塗装方法・塗り方
- 壁の仕上げ材・自然素材
- 外壁サイディング
- 外壁の調査や劣化診断
- 外壁屋根メンテナンス
- 外壁屋根塗装
- 外壁屋根塗装を安くする
- 外壁材・屋根材
- 外構エクステリア
- 天窓・トップライト
- 家具のリメイク塗装
- 小諸市
- 屋根外壁のリフォーム
- 山ノ内町
- 工事の見積もり
- 工事の費用相場と実費用
- 工事中の生活
- 工事期間
- 工場・ビル
- 御代田町
- 悪徳業者・手抜き工事
- 断熱材・遮熱工法
- 新築工事・戸建て住宅
- 施工作業の工程
- 日本家屋・和風住宅
- 暑さ対策・日除けリフォーム
- 木材・木部再生
- 未分類
- 業者の選び方
- 温泉・浴槽
- 火災保険申請・工事
- 物置設置・移動・リフォーム
- 特別教育・資格
- 玄関ドア
- 現場管理と検査
- 窓ガラスフィルム
- 結露・結露対策
- 網戸・ふすま・障子・畳
- 色選び・カラーシミュレーション
- 落ち葉・落葉対策
- 虫対策
- 補助金・助成金
- 訪問販売の手口や事例
- 躯体改修・大規模修繕
- 軽井沢
- 遮熱・断熱塗料
- 鉄部塗装
- 長野市
- 防水トップコート
- 防水工事
- 防犯・防災対策
- 雨戸・シャッター
- 雨樋の劣化・調査・修理
- 雨漏り・目視・散水・赤外線
- 雪止め・雪害対策
- 須坂市の魅力
- 風水
- 飯山市
- 養生
- 駐車場ライン引き
- 高山村
- 鳥・獣対策
ARCHIVEアーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2024年11月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年2月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2010年9月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 1998年4月
コラム
【塗料の性能はどうやって調べる?】耐久性・密着性・耐食性などを見極める評価試験の種類と方法

建築・工業・車両・住宅塗装など、さまざまな場面で使われている「塗料」。
しかし、ひとくちに塗料といっても、製品ごとに性能差が大きく、見た目だけではその違いを判断できません。
では、塗料の性能を正確に調べるには、どのような方法があるのでしょうか?
この記事では、塗料の信頼性を見極めるために行われる「塩水噴霧試験」「摩耗性試験」「暴露試験」など、主要な塗料評価試験の種類・目的・方法・評価基準を詳しく解説します。
目次
なぜ塗料の性能試験が必要なのか?
塗料は、素材の表面に膜を作って、防水・防腐・美観・耐久性などの性能を発揮する重要な保護材です。
しかし、使われる塗料が本当にその性能を持っているかは、実際に使ってみないと分からないことも多いのが現実。
そこで事前に行われるのが「性能試験」です。
性能試験の主な目的
●塗膜の耐久性の評価(屋外でどれだけ持つか)
●錆や腐食に対する耐食性の確認
●擦れや引っかきに対する摩耗性
●紫外線・湿度などへの耐候性
●素材との密着性や剥離のしやすさ
これらの試験を通じて、塗料の信頼性や長期安定性を数値で可視化できます。
塗料の性能を調べる主な試験方法3選
塗料の試験にはさまざまな種類がありますが、今回は現場でよく用いられる3つの代表的な試験方法を紹介します。
① 塩水噴霧試験(SST:Salt Spray Test)
塗装面に人工的に**塩分を含んだ霧(塩水ミスト)**を噴霧し、腐食の進行度を観察する試験です。
試験方法の概要
試験片(鉄やアルミなどの素材に塗装したもの)を用意
表面に**クロスカット(切り込み)**を入れる
試験機の中で一定時間(例:240時間)塩水を噴霧
腐食の進行度や塗膜の剥がれなどを評価
② 摩耗性試験(Taber試験など)
塗装面に対して一定の荷重で回転する摩耗輪を当て、塗膜の擦り減り具合を測定します。
試験方法の概要
回転式摩耗試験機(タバー式など)に塗装試験片をセット
規定の荷重と速度で摩擦
摩耗前後の重量差や摩耗深さを測定
「何回転で下地が出るか」「何グラム削れたか」などで評価
③ 暴露試験(屋外曝露試験)
実際の気候条件下(風雨・紫外線・塩分・砂塵など)で、塗膜の変化や劣化を長期間にわたり観察する試験です。
試験方法の概要
各地の試験場(例:沖縄・宮古島、北海道など)に塗装試験片を設置
1年・3年・5年…と長期間放置
色の退色、ひび割れ、剥離、チョーキングなどの自然劣化を観察
各試験の目的と測定できる性能項目
それぞれの試験が、どの性能を測るために行われるのかを整理しましょう。
| 試験方法 | 測定目的 | 測定項目 |
| 塩水噴霧試験 | 耐食性・防錆性能 | 錆の発生・剥離の有無・腐食範囲 |
| 摩耗性試験 | 摩擦強度・表面耐久性 | 摩耗量・回転数・塗膜の露出状況 |
| 暴露試験 | 総合耐候性・実使用環境での安定性 | 色あせ・剥がれ・ひび割れ・光沢保持率 |
目的別に見ると…
金属製品に使う → 塩水噴霧試験が重要
工場や工事現場など摩耗の多い環境 → 摩耗性試験が重視される
屋外看板や外壁塗装 → 暴露試験が必須
製品の使用用途に応じて、重視する試験結果が変わるということを理解しておきましょう。
試験環境と立地条件の重要性
試験の正確性は、どんな環境で実施されるかによっても大きく左右されます。
塩水噴霧試験の環境
温度:35℃前後に設定
塩水濃度:NaCl 5%(海水に近い濃度)
試験時間:72時間〜2000時間まで目的に応じて設定
暴露試験の実施地と特徴
| 地域 | 特徴 |
| 宮古島(沖縄) | 紫外線・塩害・高温多湿 → 最も過酷な環境で劣化が早い |
| 北海道 | 寒冷地・凍結・紫外線少なめ |
| 静岡・つくば | 標準環境として中性的な評価 |
屋根面・壁面・角度・方位などでも劣化の進行度が異なるため、設置方法にも配慮されます。
試験結果の見方と評価ポイント
各試験結果は、目視評価・定量評価・画像解析などを用いて総合的に判断されます。
塩水噴霧試験の評価基準
錆の広がり:クロスカット周辺のサビ幅(mm)
剥離の有無:塗膜が浮いた・剥がれた面積
評価グレード:JIS K 5600などに基づく段階評価(10級→1級)
摩耗性試験の評価基準
摩耗深さ(μm)や重量減少(mg)を数値化
1,000回転後の状態などを比較評価
「摩耗に強い=長持ちする塗膜」と判断できる
暴露試験の評価基準
色差(ΔE):目視では分からない色の変化も数値化
光沢保持率(%):塗膜表面のツヤの保持度合い
ひび割れ・チョーキング・剥離などの有無を写真記録
性能試験で注意すべき点と限界
塗料の試験は万能ではなく、注意すべき点もあります。
限界と補足ポイント
| 問題点 | 解説 |
| 結果が実環境と異なる場合も | 屋内の試験装置では実際の風雨や日照の複雑な影響は再現しきれない |
| 評価基準のバラつき | 試験機や評価者の違いで、若干の差が出る場合もある |
| 時間がかかる | 暴露試験などは年単位で結果が出る |
信頼性のある塗料を見分けるコツ
第三者機関の試験データが公開されているか
JIS規格やISO試験に準拠しているか
複数の試験結果で性能が裏付けられているか
これらを確認することで、性能が数字で証明された塗料を選べるようになります。
まとめ:塗料を選ぶときは「性能試験結果」に注目を
塗料選びで後悔しないためには、「見た目」や「価格」だけでなく、数値化された性能試験の結果をチェックすることが非常に重要です。
塗料の性能試験まとめ
| 試験 | 測定する性能 | 特徴 |
| 塩水噴霧試験 | 耐食性(サビへの強さ) | 金属用塗料の評価に必須 |
| 摩耗性試験 | 耐摩耗性・塗膜の強さ | 床や工業用製品に適応 |
| 暴露試験 | 総合的な耐候性 | 実環境での劣化耐性を確認 |
性能試験結果がしっかり明示された塗料を選べば、長持ちし、信頼性の高い施工が可能になります。
住宅塗装や工業製品の塗装選定において、ぜひ「試験データの有無」にも注目してみてください。